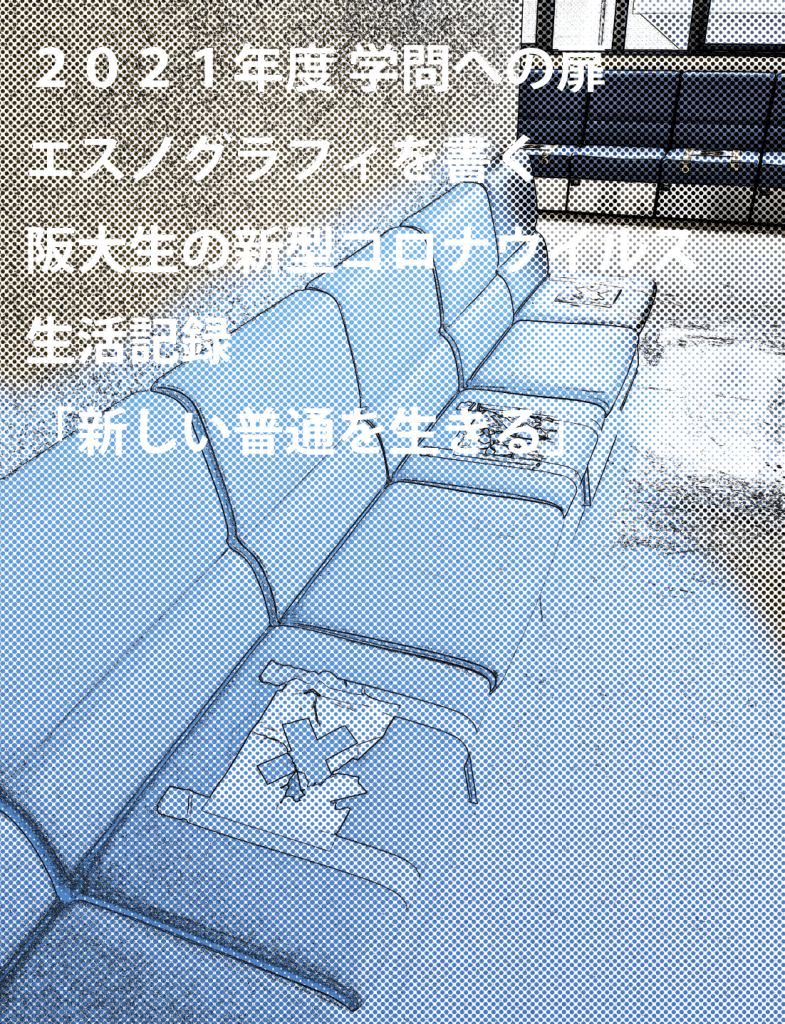以下はChat GPTを使ってアレンジを加えた桃太郎の話だ。
私はエスノグラフィを書くことがあるのだが、できれば深沢七郎風に書きたいといつも思っている。その練習のためにAIに深沢七郎風に書かせてみた。
お題はなんでもよかった。およそ多くの日本人が知っているだろう桃太郎にすることで、ストーリーではなく、文体にフォーカスを当てやすいのではないかと思った。
「深沢七郎風に」とだけAIに注文すると、だいぶ微妙な仕上がりになるので、もっと人間に寄り添った感じでとか、文章の長短をいい感じに混ぜてとか、人間を見つめる暖かさとかなしみを溢れさせてとか、いろいろと注文をつけて完成させた。(ちなみに岡山弁らしき方言はAIが勝手に気を利かせてつけてきた)。
だからこれは深沢七郎の模写というよりも、私の理想の深沢七郎なのだ。
もしもいろいろと遊んでみたい方がいれば以下のURLからアクセスできるようにしたので、試してみてほしい。
https://chatgpt.com/g/g-684b784c23648191a05353f3da550ed4-orekasi-ushen-ze-qi-lang
桃太郎
むかし、ある村のはずれに、おじいさんとおばあさんが住んでいた。
山のかげで、風の通りがよく、夏はすずしくて、冬は早く日がかげる。
畑も田んぼもなかったが、野菜と芋とを育てて、ふたりで食べていた。
おじいさんは、山へしば刈りに行った。
腰が曲がっていたので、急な斜面では立ったまま眠ってしまうこともあった。
それでも、毎朝、草履をはいて出ていった。
おばあさんは、川へ洗濯に行った。
山の水が、石の間をつたって冷たかった。
指先がかじかむと、「ああ、生きとるなあ」と思うのだった。
ふたりとも、年をとっていたが、いちおう元気だった。
たまに隣の家から味噌をもらいにくる子どもを見ると、少し黙ってしまうことがあった。
ある日、おばあさんが川にしゃがんでいると、
上流から桃がひとつ、ふわりと流れてきた。
丸くて、大きくて、赤みがかっていた。
桃は、何も言わず、ただ流れてきた。
おばあさんはそれを、黙って見ていた。
手をのばすのが、少しためらわれた。
だが、誰もいなかったし、流れてしまえば、それっきりだった。
「もったいないけえの」
そう言って、おばあさんは桃をすくい上げた。
水が、袖までしみこんだ。
冷たさが、骨にしみた。
「じいさまが、好きじゃけえな」
と、小さくつぶやいて、桃を抱いて家へ帰った。
桃は、台所の木の盆の上でしずかに割れた。
中から赤ん坊が出てきたとき、おばあさんは叫ばなかった。
おじいさんは、その声を聞いて急いで帰ってきた。
ふたりで、湯を沸かして、赤ん坊の体を拭いた。
桃の香りが、まだ肌に残っていた。
名前は、桃太郎とつけた。
ふたりとも、特に相談はしなかったが、そう呼ぶのがしっくりきた。
桃太郎は、すくすく育った。
芋をよく食べ、よく笑った。
草履をぬいで裸足で走りまわり、魚を追いかけて川に飛び込んだ。
魚は取れなかったが、水をはねさせる音が、家の奥まで聞こえた。
おじいさんは、桃太郎と一緒に薪を割った。
おばあさんは、桃太郎と一緒に味噌をこねた。
だれも、むかしのことを話さなかった。
桃から生まれたことも、鬼がいるという話も。
けれどもある日、桃太郎は、土間に座ってぽつりと言った。
「鬼ヶ島に行こうと思う」
おじいさんは、煙草を手に取ったまま動かなかった。
おばあさんは、鍋の火を弱めた。
「そうかえ」
おじいさんが言った。
「なしてかの」
おばあさんが聞いた。
桃太郎は答えなかった。
でも、その背中を見て、おじいさんもおばあさんも、もう止められんと思った。
次の日、おばあさんは米ときびを炊いて、団子にした。
味噌を少し入れたから、やや塩気があった。
桃太郎の腰に、それをぶらさげた。
「食べきる前に帰ってくるような気がするけどのう」
おばあさんは笑った。
桃太郎も笑った。
笑いながら、目を伏せた。
おじいさんは、手拭いで包んだ刀を渡した。
それは昔、村に山賊が来たときに握ったものだった。
桃太郎は、何も言わず、頭を下げて家を出た。
ふたりは見送らなかった。
ただ、玄関の戸を開けたまま、土間にしゃがんで、湯を沸かしていた。
風が吹いた。
桃の木が、枝を揺らしていた。
葉のあいだから、夕陽がちらちら見えていた。
山をいくつか越えたころ、犬がいた。
耳がちぎれていた。
遠くから見て、桃太郎は声をかけた。
「団子がある。ついてくるか」
犬はしばらく桃太郎を見ていたが、やがて近づき、黙って後ろを歩いた。
団子はあげなかった。
それでも犬は、ついてきた。
その次の日、猿が木の上で騒いでいた。
桃太郎が見上げると、猿は団子の袋を見ていた。
「欲しいか」
桃太郎が聞くと、猿はうなずいた。
桃太郎は一つだけ渡した。
猿は食べてから、地面におりてきた。
「ついてくるのか」
と聞いたが、猿は答えなかった。
でも、木の枝を伝って、桃太郎の横に来た。
そのまた次の日、空にキジがいた。
桃太郎は立ち止まって見上げた。
キジは桃太郎の頭上をぐるりと回ったあと、前の岩にとまった。
桃太郎は団子を半分に割って、岩の上に置いた。
キジは、それをつついた。
それきり、桃太郎の少し前を飛ぶようになった。
犬と、猿と、キジ。
誰もしゃべらなかったが、誰もいなくならなかった。
夜、桃太郎は火を焚いた。
猿は近くの枝にぶらさがり、犬は地面に寝ていた。
キジは離れた木にとまっていたが、目は閉じていなかった。
団子は、もうあまり残っていなかった。
でも、足りなくなったら、そのときは分け合えばいいと思った。
黙っていても、そういうふうになっていた。
次の日、海が見えた。
船に乗ったのは、村の漁師が出した舟だった。
「鬼ヶ島に行きたい」と言うと、漁師は首をかしげたが、何も聞かずに漕いでくれた。
海は思っていたより静かだった。
桃太郎は舟のへりにもたれ、犬と猿は身を寄せていた。
キジは帆の上にとまっていた。
しばらくして、島が見えた。
岩がごつごつしていて、赤い屋根のようなものがいくつか見えた。
煙が出ていた。
鬼の家だろうか、鍋を焚いているのだろうか。
舟を降りて、浜を歩いた。
誰も出てこなかった。
犬が鼻を鳴らした。
猿は木をつかんで、上へ登った。
キジが低く鳴いた。
その声に、鬼が出てきた。
赤い顔をして、金棒を持っていたが、片足を引きずっていた。
目は大きかったが、何かをじっと見るような目ではなかった。
鬼は叫んだ。
何を言っていたかは、よく聞こえなかった。
桃太郎は、腰の刀を抜いた。
犬が吠えた。
猿が背中から飛びかかった。
キジが空から急降下した。
鬼は驚いたようだった。
転び、転がり、何かを叫び、
やがて、地面に伏した。
桃太郎はそれ以上、手を出さなかった。
鬼は、もう立ち上がろうとしなかった。
しばらくして、他の鬼たちが、奥から出てきた。
誰も戦おうとしなかった。
ある者は腰を抜かし、ある者は泣いていた。
桃太郎は、持っていた袋を開いた。
残っていた団子を、三つ取り出して置いた。
「これは置いていく。腹が減ったら食べてくれ」
鬼たちは何も言わなかった。
桃太郎は、犬と猿とキジと一緒に舟へ戻った。
舟はまだ浜にいた。漁師は網を直していた。
帰りの舟では、誰もしゃべらなかった。
海が青くて、空がまっすぐだった。
村に帰ったのは、夕方だった。
家の前には、火がともっていた。
おばあさんが、鍋のふたを開けていた。
おじいさんは、薪を割っていた。
桃太郎は黙って玄関に立った。
おばあさんが、ふと顔をあげた。
「おかえり」
それだけ言って、また鍋に目を戻した。
おじいさんは、薪の束をひとつ持ち上げて、
「団子は、足りたか」と言った。
桃太郎は、うなずいた。
犬はそのまま庭に寝ころび、猿は柿の木に登った。
キジは屋根の上で羽をとじた。
夕飯の匂いが、土間にひろがった。
その匂いのなかに、桃の香りが、まだ少しだけ残っていた。